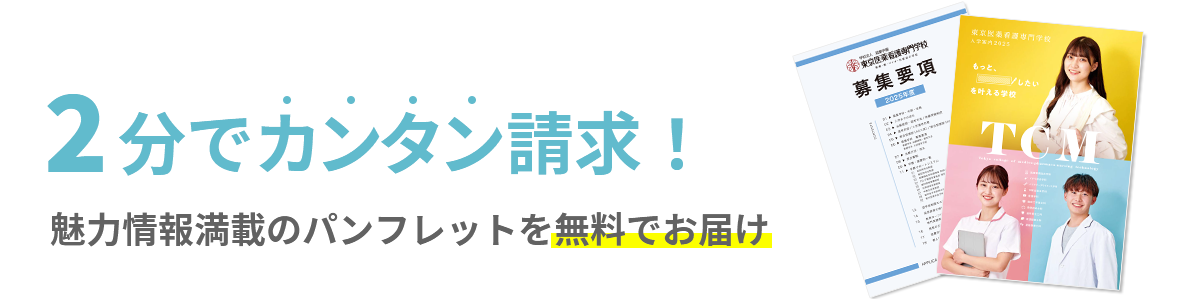2024.08.09
視能訓練士
視能訓練士(ORT)になるには?大学・短大・専門学校からなる手順を解説!
「視能訓練士になるにはどの学校に進学したらいいだろう?」
進路を決める学生のなかには、このような悩みを抱えている方もいるでしょう。視能訓練士(ORT)になるためには、大学、短大、専門学校のいずれかを経て国家資格を取得する必要があります。
この記事では、視能訓練士になるための進学方法と、おすすめの進学先について解説します。
- 記事の概要
視能訓練士は通信では取得できない国家資格
視能訓練士として働きたい学生の中には、通信講座で資格を取得したいと考えている方もいるかもしれません。 しかし、視能訓練士の資格は通信講座では取得できません。 視能訓練士の資格が通信教育で取得できない理由には、以下のようなものがあります。- 実践的技術の習得
- 医療現場での経験
- 高度な専門知識の獲得
- 医療職としての倫理観の形成など
視能訓練士になるには
視能訓練士を目指す方法として、大学や短大経由と専門学校経由の2つの道があります。 それぞれの方法の特徴と進路について、詳しく解説します。大学・短大から視能訓練士を目指す
大学や短大での学習は、幅広い教養と基礎知識を身につけた上で、視能訓練士の専門教育を受けます。1年制の視能訓練士養成学校へ入学する必要がある
視能訓練士の国家資格を取得するためには、一般の大学(4年制)や短大(2年制)を卒業後、1年制の視能訓練士養成学校に進学します。 この1年間で、視能訓練士に特化した専門知識と技術を集中的に学びます。 大学や短大を経ることで、幅広い教養と多角的な視点を持つ視能訓練士を目指せるでしょう。しかし、2つの学校を卒業する必要があるので、総学習期間が長くなり、時間と費用がかかる点がデメリットです。専門学校から視能訓練士を目指す
専門学校の視能訓練士科では、3年または4年の課程で必要な知識と技術を学びます。 視能訓練士になるための専門教育に特化したカリキュラムを受け、短時間で実践的な技術や知識を集中的に学べる点がメリットです。 また、専門学校は就職先や業界とのコネクションもあるので、就職活動時に効率よく内定を取得しやすい点も特徴です。 大学や短大、専門学校のどちらも、最終的に国家試験を取得することで、視能訓練士として仕事に従事できます。 国家試験合格率や就職実績などを参考に、志望校を選択しましょう。視能訓練士を目指す学生に専門学校がおすすめな理由
視能訓練士を目指す学生にとって、専門学校は資格取得に特化したカリキュラムが最大の魅力です。 具体的には、以下のような特徴があります。- 実践的な授業
- 充実した実習環境
- 国家試験対策など
東京医薬看護専門学校の視能訓練士科
東京医薬看護専門学校の視能訓練士科は3年制で、「攻めの視能訓練士」と「守りの視能訓練士」の育成に力を入れています。攻めの視能訓練士とは
攻めの視能訓練士は、スポーツで重要になる「視る能力」を検査し、サポートするのが主な役割です。 多くのスポーツでは、広い視野や速いものを正確に視る力が必要です。 そのため、以下のような現場で視能訓練士が活躍しています。- スポーツ選手などの検査
- アスリートのトレーニング
- スポーツドック
- リハビリテーションクリニックなど
守りの視能訓練士とは
守りの視能訓練士は、子供からお年寄りまで、幅広い年齢の視力を支えるのが役割です。 視力の異常だけではなく、眼鏡やコンタクトレンズを作る際の検査など、私たちの日常をサポートしてくれます。 守りの視能訓練士は、患者一人ひとりの生活に寄り添うことのできる、やりがいのある仕事です。視能訓練士の4つの仕事内容
視能訓練士の仕事内容は、主に以下の4つです。- 視能矯正
- 視能検査
- 健診(検診)業務
- ロービジョンケア
1.視能矯正
視能矯正は、視能訓練士の専門性が最も発揮される分野です。 主に以下の症状に対して検査を行います。- 斜視
- 弱視
- 眼精疲労
2.視能検査
視能検査は、眼科診療の基本となる重要な仕事です。 具体的な検査項目は、以下のとおりです。- 視力検査
- 眼圧検査
- 屈折検査
- 眼底検査
- 視野検査など
3.健診(検診)業務
健診業務では、主に以下の役割を担います。- 3歳児健康診査
- 就学時健康診断
- 生活習慣病予防健診
- 企業健診など
4.ロービジョンケア
ロービジョンとは、視覚に障害を受け「見えにくい」や「まぶしい」などの不自由をきたしている状態です。 ロービジョンケアは、視覚障害者の自立と社会参加を支援する重要な仕事です。 主に、以下のような仕事を担当します。- 視機能評価
- 拡大鏡、単眼鏡、遮光眼鏡、拡大読書器などの選定
- 日常生活上の工夫や支援機関の紹介など
視能訓練士としての働き方
視能訓練士として働く際は、主に病院や診療所、健診センターなどで働くのが一般的です。 日々の業務を通じて経験を積むことで、より高度な検査などを担当し、キャリアアップの道も開かれています。 視能訓練士は、人々の「見える」を支える重要な職業です。 高齢化社会の進展や、デジタル機器の普及に伴う眼の健康への関心の高まりから、専門的な知識と技術を持つ視能訓練士の需要は今後も増加すると予想されます。 専門学校での学びは、将来性のある視能訓練士への大きな一歩となります。 東京医薬看護専門学校の視能訓練士科では、病院実習と国家資格対策を効率的にできる環境が整っているので、視能訓練士を目指す学生におすすめです。